海外の情報教育の現場から
アメリカにおける情報教育の動向
岩手県立大学ソフトウェア情報学部教授 鈴木克明
はじめに:インターネットによる動向調査
ゴア副大統領の発案でクリントン政権の重要政策の一つとなった情報スーパーハイウェイ構想で知られるアメリカの情報教育はどのように展開しているのだろうか。WWWを用いて最近の動向を調べた結果、(1)1998年秋に全米の公立学校のインターネット接続教室の割合が半数を越え、児童生徒12人に1台の割合でインターネットに接続しているコンピュータが設置されるに至ったこと、(2)1998年度から年間2700億円相当の補助が、情報格差を縮めるという方針の下に連邦政府から支出されており、学校間格差がなくなりつつあること、(3)先進的な取り組みの中から『学校におけるテクノロジ−利用を評価するためのガイドブック』が教師向けにまとめられ1998年に公刊されたことなどがわかった。なお、この調査はすべてインターネットを経由して行ったものであり、現地へは一度も足を運んでいない。海外の事情を知るという目的のためにインターネットがどの程度活用できるようになったか、限界はどこにあるのか、という点にも注目していただければ幸いである。
1.半数を越えたインターネット接続教室
クリントン政権は、2000年1月1日までに「全米すべての図書館、病院、教室をインターネットに接続すること」を公約に掲げ、関連諸策を講じてきた。日本においては、文部省が1999年1月にインターネット接続完了の目標を2001年度に繰り上げて話題を呼んだが、日本の「全校」接続に対して、アメリカの目標は「全教室」である。連邦教育局が(6月末に公刊予定の印刷版に先立って)1999年6月7日にインターネット上でリリースしたWeb版報告書『教育の現状1999』<注1>(A4版のPDFファイルで375ページ)によると、1998年秋の調査でインターネットへ接続している公立学校は89%と推定された。同じ調査で、インターネットへ接続している教室は推定51%と初めて半数を越え、前年同期の推定値27%から飛躍的に伸びた。この調査で「教室」とは授業が行われる部屋すべてを母数としており、一般教室、図書室、メディアセンター、コンピュータ教室などを含むものである。1994年からの推移を同報告書より引用して図1に示す。
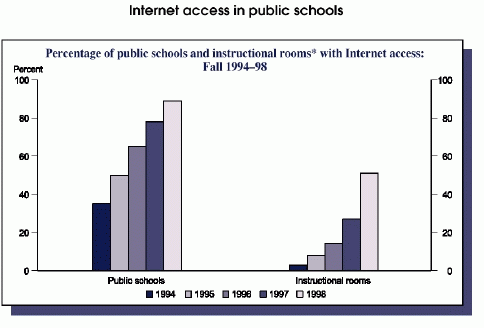
図1.インターネット接続公立学校と接続教室の推移
出典:アメリカ連邦教育局『教育の現状1999』p.37<注1>
この調査を実施した国立教育統計センターが1999年2月付でインターネット上に公開した速報<注2>によれば、同調査で公立学校でのコンピュータ1台当たりの児童生徒数は推定約6人であった。大統領諮問委員会が1997年3月に答申した「学校でコンピュータを効果的に活用するための許容比率は1台あたりに4〜5人」というレベル<注3>に接近したとしている。つまり、班に1台のグループ学習であれば、全校一斉に、すべてのクラスでコンピュータを使った授業が同時に実施できるだけのコンピュータ台数が揃いつつあることになる。
この調査では、学校規模、学区、人種、経済状態などからの不平等が生じているかどうかも分析している。その結果、もっとも不平等が目立つ指標として、児童生徒数が300人未満の小規模校で1台あたり約4人であるのに対して中規模校では1台あたり6人、1000人以上の大規模校では1台あたり7人と、学校の規模によって差があると報告している。仮に200人の小規模校であれば50(200÷4)台、1400人の大規模校であれば、200(1400÷7)台が設置されている計算になる。学校規模によらずに1校あたり42台をもって「一人1台」と計算する日本の整備方針との違いが読み取れよう。
インターネットに接続しているコンピュータについての調査結果では、1台当たりの児童生徒数は推定12人であった。つまり、学校にあるコンピュータの2台に1台はインターネットに接続されているという計算が成り立つ。インターネットへの接続形態も専用線利用が伸びており、推定65%になっていた。一方で、1994年の調査で74%あったダイアルアップ接続は、今回の調査では22%に減少していた。
2.年間2700億円の政府補助:Eレート
前項で概観したアメリカの急速なインターネット環境の整備は、1998年度より始まった政府補助によるところが大きい。連邦教育局教育工学室のホームページ<注4>によると、学校と図書館を対象に通信関連コストの一部を政府が補助する「ユニバーサルサービスプログラム」(通称Eレート)は、1996年に施行された通信法に基づいて、連邦通信委員会が1997年5月7日に採択したものである。情報格差を縮めるという方針の下に、経済的必要度と所在地(都市部か地方か)に応じて契約総額の20%〜90%を連邦政府が補助するために年間22.5億ドル(2700億円相当)の予算を確保した。補助率は都市部より地方に厚く、また、給食給付金をもらっている児童生徒の割合が高い学校ほど経済的必要度が高いとみなされ高率になる。給食給付金をもらっている児童生徒が半数以上在籍する学校(全米の32%が該当)では、都市部・地方ともに、補助率は80%以上に設定されている。補助は1998年1月1日より開始され、それ以前に契約した通信関連サービスおよび新規のものの両方を対象として審査の上、予算が尽きるまで的確と認められるものすべてを補助する(最後の2.5億ドルについては、経済的な困難校を優先)。補助対象は、インターネット接続費用(T-1からダイヤルアップまで含む)のみならず、ネットワークサーバ、ハブやルータ−、配線などを含む校内LANの構築やメンテナンスに関わる作業など広範囲に及んでおり、「学校や図書館が、最も効果的で効率的に自分たちのニーズを満たすと信じるサービスが得られるように最大限に柔軟に対応する」としている。
つまり、日本の先進的プロジェクトにみられたような一定のセットで提供するのではなく、自分たちでネットワーク環境を自由に設計して契約し、その総額の何%かを連邦政府が補助するという方法がとられている。応募できるのは公立学校のみならず、私学や「チャータースクール」、公立図書館、私立図書館なども含まれている。
初年度のEレートへの応募は、1998年4月15日に締め切られた。3万件を越す応募があり、補助要求総額は20.2億ドルに達した。そのうちの70%は、2万5千ドル未満の補助要求(55%は1万ドル未満)であり、補助要求総額の53%は最下層の経済的困難校によるものであった。このことからも、情報格差の解消に役立っていると連邦教育局は評価している。
Eレートの審査・管理機構であるユニバーサルサービス管理会社 (USAC) の学校・図書館部門<注5>によると,初年度の補助は,審査を経て1998年11月から1999年2月の間に10回に分けて認定・交付された。2万6千余件への補助総額は16.6億ドルであった。交付金額の76%は,単独の学校ではなく学校区に交付された。
Eレートの審査にあたっては,「テクノロジー計画書」の提出が義務づけられた。ハードウェアの整備のみでは教育効果は保証できないという立場から,情報テクノロジーとして整備したい物理的環境と教員研修プログラムを結び付け,カリキュラム改善が実現できる計画かどうかが審査された。3年間を視野に入れた計画を提出させ,とくに,次の5つの基準を重要視した。
- 教育向上に通信手段と情報テクノロジーを役立たせるための明確なゴールと現実的な方略
- 上記目的を達成させるための現職研修計画
- 上記目的についての評価の計画
- それらを実現するために必要な予算措置
- 進歩をモニターし,技術発展に伴う計画変更を随時実行するための中間的評価の計画
3.『テクノロジ−利用評価ガイドブック』
1999年6月17日付で、今年度のスタースクールプログラムの選考結果が公表された<注6>。全米各地から応募された教育改革プロジェクトの中から選ばれたのは、中学校数学の改革プロジェクト(カリフォルニア州)、親と子の遠隔通信の基礎としての「読み手になる」(コネチカット州;衛星利用)、英語獲得のための分散協調環境(ハワイ州)、第2母国語としての英語自作教材共有化プロジェクト(ニューメキシコ州)、矯正施設向けの成人学習ネットワーク(ワシントン州)の5件である。それぞれに対して、これから5年間、毎年約200万ドル(2.4億円)ずつが支給される。いずれも、インターネットをはじめ、情報通信テクノロジーを生かした新しい教育改革のための協同プロジェクトであり、その対象は広範囲に及んでいることが読み取れる。スタースクールプロジェクトは、連邦教育局が1988年から取り組んできたものである。これまでに、全米各州から6000を越える学校の160万人が参加し、様々なテーマで、様々な学習者たちを結び付け、学習素材を開発し、教員研修を促進し、教育変革の過程に果たすテクノロジーの役割と評価についての新しいアイディアについての研究を押し進めてきた。
1998年12月、スタースクールプロジェクトの一つ「テクノロジーについてのリテラシーに挑戦する基金」を実施する中で培われたノウハウをまとめた『学校におけるテクノロジ−利用を評価するためのガイドブック』が教師向けにまとめられ、インターネット上に公刊されている<注7>。
A4版のPDFファイル約120ページからなるガイドブックは、研究や評価についての基礎知識に弱い教師が「情報教育コーディネータ」に任命されたことを想定し、投入された資金に見合うだけの教育効果があったかどうかを評価するための手順を、分かりやすく説明したものである。冊子に目を通すと、子どもと一緒に教師も変わっていこうとする姿勢や、情報教育を通して自分たちの手で新しい学校をつくっていこうという姿勢が見て取れる。できれば翻訳をして,日本の先生方にもぜひ見てもらいたいものだと思った。
6000人の児童生徒(4小学校、2中学校、1高等学校)を擁する学区が20万ドルの補助を受けてインターネット接続のためのメディアセンターをつくり、夏休みに現職研修を実施したという仮想的な事例を引きながら、6ヶ月間で何らかの評価データを提出する仕事を任されたキャッシーが直面する様々な課題を一つずつクリアーしていく。その過程で評価の手法を説明し、ワークシートを用いた評価プロセスを提案している。中に含まれているワークシート類を含めてすべて著作権をクリアーしていることが明記され、複製が自由にできるように配慮されている。
このガイドブックの公刊に象徴されるように、また、提案されている評価手法に具体化されているように、アメリカでは情報教育にもアカウンタビリティ(説明責任というよりは結果責任の意)の原則が貫かれている。インターネットを入れたならば、それがどの程度使われているのか。子どものリテラシーはどの程度伸ばすことができたのか。それが、学力の向上につながっていくのか。現職研修を実施したならば、研修の時期や内容は妥当であったのか。教員にどの程度実力がついたのか。研修が授業を変えたのか。
これらの質問に対して、どのレベルまでの結果が求められているのか。また、それが実現できたかどうかをどうやって証拠だてるのか。評価の専門家に頼ることなく、内部的に評価を実施できるワークシートが用意されており、実施者自らが評価しながら改善していく形成的評価の思想を実現する道具にもなっている。巻末には、児童生徒のテクノロジー利用実態調査票、教師のテクノロジー接触実態調査票、現職研修調査票、コンピュータ利用技術自己評価チェックリスト(初級・中級)、整備ニーズ分析調査票、管理職用調査票、ハードウェア調査票など、多彩なアンケート用紙も提供されている。
おわりに
今回インターネットを通じてアメリカの情報教育をめぐる動向を調査して,国家目標に向って相当急激に条件整備が進んでいることがわかった。情報格差について細心の配慮がなされており,また,巨額を投資すると同時に,有効利用を実証する姿勢が求められていることが再確認できた。連邦統計局のサイトでは,1997年10月に家庭,職場,学校でのコンピュータやインターネット利用についての調査<注8>を実施したことや,調査項目として「週何回コンピュータを使った授業があったか」「今家庭にあるコンピュータで最新のものは何年に購入したか」などの具体的なものが含まれていたことが公表されていた。しかし,調査結果はごく一部しかインターネット上では公開されておらず,CD-ROMに納められた生データの購入申し込みを受け付けていた。これもまた,アメリカ的ということであろうか。インターネットを用いた調査の限界でもあった。
注
- http://nces.ed.gov/pubs99/condition99/pdf/1999022.pdf
- http://nces.ed.gov/pubs99/1999017.html
- 答申の全文が以下に公開されている。
http://www.whitehouse.gov/WH/EOP/OSTP/NSTC/PCAST/k-12ed.html
- http://www.ed.gov/Technology/eratemenu.html;最終更新日1998年6月9日
- http://www.sl.universalservice.org/;最終更新日1999年6月23日
- http://www.ed.gov/prog_info/StarSchools/
- http://www.ed.gov/pubs/EdTechGuide/
- http://www.census.gov:80/apsd/techdoc/cps/oct97/toc.html