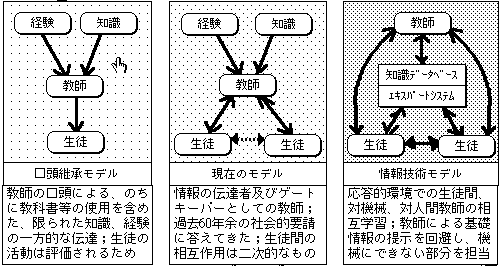『放送教育』1992年12月号原稿
シリーズこれからの放送教育を考える
情報社会型の放送教育(1)
東北学院大学 鈴木 克明
「これからの学校をどうするのか?」という問い
放送番組の利用者の立場から「これからの放送教育」を考えるとき、「どのような番組を流してもらいたいのか」という問題設定よりも、「放送教育でこれからの学校をどんな風に変えていくきっかけをつくるのか」という問題に興味をひかれる。「別に放送番組を使わなくても授業はできる」という安心感があるからだろうか。
昨今、学校へのコンピュータ導入や新しい指導要領の施行、指導要録の改訂など、様々な<変化>が主に学校の外側から学校を襲撃している。その底流には、叫ばれて久しい「情報化社会」の到来による社会の変化に学校が取り残されないように、また、「情報化社会」に必要な能力を培って子どもたちを世の中に送りだせるようにという願いがある。いわんや来たるべき社会の創造者として世の中の変化を先取りする人材を学校が育成し、社会を望ましい方向に変化させていくという学校教育本来の責務を自覚したとき、「これからの学校をどうするのか?」という大上段にふりかざした問いが気にかかる。
このシリーズを拝読すると、放送教育の歴史は、もともと「教育の現状を問い直す」営みとして捉えうることがわかる。しからば暫くの間、教育実践の雑踏を離れて、少し遠い未来のことを考えてみることにおつきあい願いたい。
情報活用能力を育てる学校
新しい指導要領によると、これからの学校で耕すべき力の一つは「情報活用能力」であるという。それは、大量の情報をすばやく学習する情報処理の力ではなく、「情報を自ら主体的に探し、加工し、つくりだす力」という意味をもつそうだ。もしも学校がもともと社会に出るために必要な知識を得るところであり、情報を提供されるところだとするならば、本当にそのような力を育てることができるのであろうか。「学校で得た基礎知識をもとに、あとは自分で情報活用をすればよい。まずは基礎基本をしっかり身に付けることが肝要である。」といった反応も無視できまい。
確かに、本気で「情報活用能力」を育てようと考えるならば、たとえば放送番組が直接的に「情報を提供すること」を控えなければならないことになる。しかし、何らかの情報を提供しないでは放送番組は成立しない。とんだ自己矛盾である。視聴するだけで「情報活用能力」が育つ放送番組などありえない。提供されてしまった情報を自ら探しだすことはできないからである。そういったら言い過ぎであろうか。
「情報を提供すること」と「情報活用能力」を育てることとの矛盾は、何も放送番組だけにとどまらない。この矛盾は、現在の学校教育全体が抱える矛盾でもある。大阪大学の水越敏行は、その著書『メディアを生かす先生』の中で授業展開のために教師は少なくとも2本の包丁をもたなければならないという比喩で教師主導型の授業の在り方に疑問を投げかけている。すなわち、プロの料理人が調理する材料に応じて数々の包丁を使い分けるように、「一斉授業で、あるまとまった知識を伝達して理解させる場合の包丁」とは別に、「生徒が調べているところを回っていって、その生徒に的確な調べ方や学習の仕方を指示するときの包丁」をもつ必要がある。情報活用能力の育成につながる指導法はむしろこの(あまり使われない)2本目の包丁のことではないか、という指摘である。
もしも、これまでの放送教育がこの喩えでいう1本目の包丁の代役として用いられてきたとすれば、それによって「情報活用能力」の育成は望めないし、また学校教育の在り方そのものに疑問を投げかけることにもならない。矛盾にさらされているのは、情報の送り手が教師であれ放送番組であれ「権威ある情報源」であって、それを整然と受け取る「受け手」として子どもたちをみなすという類の学校観である。すなわち、もし本気で「情報活用能力」を育てたいと考えるならば、今の学校そのものの在り方を見直すことを避けることはできない。「情報の伝達」「基礎知識の習得」が学校の本務であるとするならば、それと同時に「情報活用能力」を育てることは至難の技であろう。あるいは本当に問われているのは、2本の包丁のバランスをどうするかということなのかも知れない。
これまでの学校と学校改革の動き
なぜ学校が今あるような「知識伝達」を重視することになったかの理由をその時代背景に求める社会学者のアプローチには説得力がある。「第3の波」であまりにも有名なトフラーによると、現在の学校は産業革命(第2の波)の産物であり、学校の在り方には工場労働者の養成という要求が反映されているという。学校では、基礎的な読み書き算盤を教えると同時に、「その裏にははるかに大切な裏のカリキュラムが隠されていた。内容は3つで、今日でも産業主義の国では守られている。それは、時間励行と従順と機械的な反復作業である。…中略…第2の波が何世代もの若者を電気機械技術と流れ作業の要求する従順で集団的な人間に訓練していったことは否定できない。」(中公文庫版、50-51頁)
確かにこれまでの日本の学校から「優秀な労働者」が育てられ、それが今日の日本の繁栄の基礎を築いてきたという指摘には反論しにくい。しかし、そのことがこれからもこのままでいいという論拠にはなりづらい。なぜならば、(また社会学者の説くところによると)時代背景が変化し、社会が学校に要求するもの、もしくは学校が社会に貢献できることが以前と同じではないからである。本論の冒頭に述べた学校に対する「外圧」とは、まさにこの社会の変化に他ならない。その「外圧」に対する学校がなすべきことの一つが「情報活用能力」の育成という課題として捉えられているのである。
アメリカ合衆国では、ブッシュ政権のもとで始められた「2000年のアメリカ」プロジェクトを皮切りに、今学校改革の嵐が吹き荒れている。これからの情報技術社会における学校の在り方を具体的に提案し、それを試行するプロジェクトを連邦政府が公募し、選定の上莫大な研究資金を与えるという画期的なアナウンスをしてから、各州政府も独自に同様なプロジェクトを支援し始めた。これによって、教育工学界(アメリカでは放送教育の研究もこの中に含まれる)は特に活気づいてきた。今の学校教育の現状を何とかするとしたら、その担い手は我々であるという自覚に燃えてのことである。
フロリダ州の学校改革プロジェクトを代表するフロリダ州立大学のブランソンは、学校の仕組みそのものを変えていかなければこれ以上の向上は望めないという立場をとる研究者の一人である。ブランソンによれば、現在の学校では、教師も管理職も行政職も、各自の能力の限界まで努力しているにもかかわらず、問題が山積している。これは、長年良く機能してきた学校の仕組みが社会の変化とともに「時代遅れ」になった結果であり、現在の仕組みのままで学校が達成可能な成果のうち97%はすでに達成してしまっている、という主旨の「上限到達(アッパーリミット)仮説」を主張している。
ブランソンは情報技術の学校への単なる導入に反対の立場をとり、つぎのような問題を投げかける。「コンピュータ」を「放送」に読み換えると、大いに参考になる。「もし『先生方に教室でコンピュータを使ってもらうにはどうしたらよいだろうか?』ということを問い続けても、あまり多くの進歩は期待できない。『情報技術を教育の抜本的な向上に役立たせるにはどうしたらよいのか?』を問うべきである。その際、現在の教師による伝達モデルを絶対視しているうちは発展の望みは薄い。」(引用文献10頁)
学校の情報技術モデル
ブランソンが提案する新しい学校の仕組みは、学校の情報技術モデルである(図1参照)。現在の学校モデルで中心的な「情報コントロールタワー」としての教師は姿を消し、かわりに情報技術で実現した「知識の貯蔵庫(データベース)」とコンピュータ上に実現した種々の「専門家(エキスパート)システム」を子どもと教師が取り囲んでいる姿が描かれている。教師によって設定された問題をめぐって、子どもたちは自分に必要な情報を「専門家」からアドバイスを受けたり「貯蔵庫」から自分であるいは仲間と探りながら、加工し、自分たちなりの情報をつくりだしていく。そこでは、ちょうど水越が2番目の包丁として位置づけるような、「情報活用能力」の育成につながるような、活動的な授業が主として営めるような学校が描かれているのではないか。
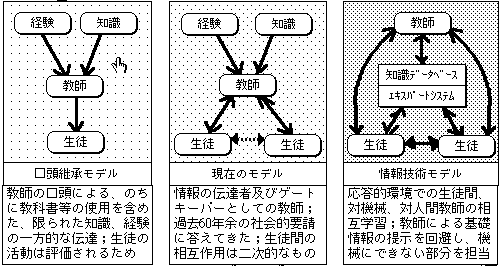
****
図1 ブランソンの学校モデル このあたりに挿入(550字分程度)=14行x40字
****
ブランソンのモデルは夢物語かも知れない。特に文化的背景を考えると、日本ではそんなに急に実現しそうもない。しかしながら、ブランソンの次の主張は、注目に値する。もしも放送を含む情報技術で教師の手助けをしようと考えた場合に、何を肩代わりするのがよいのかを示唆しているからである。「情報技術モデルの学校では、機械システムからまず学ぶ経験を可能な限り子どもたちにもたせる。教師は教科内容の情報提供を反復的に繰り返すためではなく、例外や問題点に対処するために待機する。黒板とチョークを使って、年間を通して一日中講義することを強いるやり方は、教師の創造力を最大限に活かしている姿とは思えない。」次回は、情報社会型の放送教育の実現について考えたい。
引用文献
Branson, R.K. (1990, April) Issues in the design of schooling: Changing the paradigm. Educational Technology, 7-10.