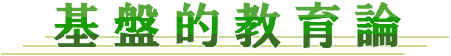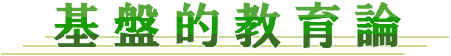
担当教員: 鈴木克明、渡邊あや
開講年次: 1年前期
後続科目: eラーニング実践演習I、特別研究I
概要:
教育学の視点からeラーニング実践を点検するための基礎を培う。
教員免許課程における教育原理・教育方法論・教育心理学のエッセンスと教授設計理論の基礎について短期間でカバーできる。教育学の基礎知識が不足している入学生のための補講的基礎科目。
注記:
この科目は、2008年度からはカリキュラム改訂により「自由科目」となりましたので、修了要件の単位としてはカウントされません。ただし、上記の「後続科目」を受講するための要件になりますので、履修免除者以外は、1年後期開始前には完了しておく必要があります。ご注意ください。
履修上のアドバイス:
過年度の受講生からの感想として4ブロックはとっつきにくかったとの意見が寄せられています。1ブロック終了後は、2・3・4ブロックのどれから学習を進めても構いません。興味が持てそうなことからやる、興味が持てそうなことはあとに残してご褒美にする、など好みに応じて作戦を立てて取り組んでください。
テキスト:ジョン・デューイ(1938) 「経験と教育」 講談社学術文庫(市村尚久訳、2004)¥798
※このテキストは(第11・12回)で使いますので、用意してください。
参考書:沼野一男(1986)「情報化社会と教師の仕事」国土社(教育選書8)¥1,377
※この参考書の一部は第13回に関連します。入手が困難な場合は、ご相談ください。鈴木の尊敬する師匠の名著です。
~お知らせ~
2009/04/17
第1回のショートビデオの形式を変更し、更新しました。(内容は同じものです。)
※ 基盤的教育論のシラバスは こちらからご覧ください。
下記の課題のすべてに6割以上得点することが単位取得の最低条件です。
|
| [課題1] リフレクションペーパーI |
講義第2回課題としてアップロードする。受講前の教育に関する自説(考え方、哲学、見方、やり方など)をまとめる。
つまり、現在(学習指導に関する)職務 を実施する際のやり方、明示的・暗示的に寄せている期待、
どうしてそのような考え方をもつに至ったか、自分自身が学習者として経験したこと、重要な教師との出会い、
経験した教育課程やプログラムなどを述べる。参考文献を引用する必要はないが、上記の自説形成に強い影響を
与えた書物等がある場合はそれを明記 のこと。受講者同士で閲覧し、相互にコメントをつける。
アップロードされたペーパーの中身と相互コメントの両方を採点の対象とする。
|
| [課題2] 学習指導・評価論の理解と参加・貢献度 |
ブロック2の講義資料として指定される文章についての問いに答え、理論をしっかり理解したことを証明する。
理論をよく理解していることを表現できたか、個人の経験に直結した解釈ができているかで評価する。
また、ブロック2の掲示板の書き込みにどの程度積極的にコメントし、それが全体の議論の深まりに貢献したかを評価する。
|
| [課題3] 学習心理学理論の理解と参加・貢献度 |
ブロック3の講義資料として指定される文章についての問いに答え、理論をしっかり理解したことを証明する。
理論をよく理解していることを表現できたか、個人の経験に直結した解釈ができているかで評価する。
また、ブロック3の掲示板の書き込みにどの程度積極的にコメントし、それが全体の議論の深まりに貢献したかを評価する。
|
| [課題4] 教育学理論の理解と参加・貢献度 |
ブロック4の講義資料として指定される文章についての問いに答え、理論をしっかり理解したことを証明する。
理論をよく理解していることを表現できたか、個人の経験に直結した解釈ができているかで評価する。
また、ブロック4の掲示板の書き込みにどの程度積極的にコメントし、それが全体の議論の深まりに貢献したかを評価する。
|
| [課題5] リフレクションペーパーII |
講義第15回課題として第1稿を提出。他の受講者からの相互コメントを参考に改訂し、本提出する。
この講義を受けることによって自説がどのように変化・深化したかをまとめる。
講義で学んだどの理論が最も影響を与えたか、自己の学習方法や学習指導に係る職務遂行に将来どのような変化が起きそうか、
その理論がインパクトを与えた理由は何かなどを述べる。最終提出されたペーパーと相互コメントの両方を採点の対象とする。
|
|