第2章「調査結果」
2.2.放送番組についての教師の期待
学習指導要領と放送番組の関連で、どのような番組を使いたいかを尋ねた質問(複数回答可)【質問項目2-1】では、「学習指導要領の内容の範囲を詳しく扱った番組」を希望する回答者(71人)よりも、「学習指導要領の内容に多少の発展的な要素を加えた番組」を希望する回答者(127人)の方が多かった。また、「学習指導要領の内容から大きく発展したものを扱った番組」を求める声も回答者の3割(45人)を越えた。
図表2−12に、学校放送番組は授業でどのように役立つと考えているか【質問項目2-2】に対する回答を示す。
図表2−12 放送は授業でどのように役立つと考えるか(複数回答可)
—————————————————————————————————
映像資料として役立つ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124人
発展学習への動機付けとして役立つ・・・・・・・・・・・・・・107人
子どものこころを揺り動かすのに役立つ・・・・・・・・・・・・96人
授業の単調さを解消するのに役立つ・・・・・・・・・・・・・・50人
教師がいないときの自習用に役立つ・・・・・・・・・・・・・・・6人
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8人
(学びかたを学ぶ(2)、学ぶ喜びを教える、楽しく学べる、復習(2)、
発展学習(2)、まとめ(2)、メディアリテラシー育成、教師できることを拡張(2)、
教師自身への啓発(授業づくり、知識補完、視野を広げる)、番組構成が授業
構成の参考、計画的系統的な学習カリキュラム作り)
—————————————————————————————————
過去に授業で利用した(あるいはあなたが視聴した)番組で,現在指導している子どもにもあなたがぜひ視聴させたいと思うものがあるかどうかとの問い(自由記述式)【質問項目2-3】には、回答者の71.8%にあたる102人からの具体的な回答があった(「特にない」と書かれた回答などを除く)。回答の一覧を番組ごとに整理して資料2−2に示す。
回答の傾向として、次の3点を指摘しておく。(1)現在放送中の「総合的な学習の時間」向けの番組が多くあげられている。現在の番組が好評ともとれる一方、過去の番組を余り知らない回答者が多いととることもできる。(2)一般番組では、NHKスペシャル「人体」や「生命・40億年はるかな旅」、あるいはプロジェクトXなど、スケールが大きく映像のインパクトの強い番組を見せたいという声が多かった。(3)過去の学校放送番組については、「にんげん家族」「みんな生きている」の特定の回をとくに取り上げる回答や、凝った演出で評判になった「虹色定期便」や、森末慎二氏が出演した「はりきって体育」などの視聴印象の強いものが目立った。
利用しやすい番組の長さに対する回答【質問項目2-4】は、「15分」が大多数(回答者の64.8%にあたる92人)を占め、次いで「10分」の22.5%(32人)であった。その他の選択肢(30分、20分、5分)を回答した者はわずかで、「45分」との回答はなかった。図表2−13に、担当学年ごとの回答傾向を示す。担当学年、回答者の性別、あるいは教職年数で、利用しやすい番組の長さに違いはなかった。番組の長さについての意見(自由記述)は、回答者の67.6%にあたる96人から寄せられた。資料2−3に、その一覧を回答傾向別に整理して示す。
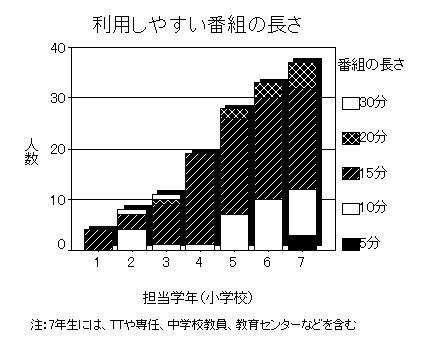
図表2−13 利用しやすい番組の長さ(担当学年ごと)
図表2−14に教職年数ごとのシリーズ化についての意向を示す。教職年数ごとで異なる傾向は見られなかったものの、20話継続を希望する回答者は、教職年数10年未満の回答者にはいなかった。シリーズ化についての意向と、性別や担当学年、インターネット授業実践度との間に、統計的な関係はなかった。回答者の54.2%にあたる77人から寄せられたシリーズに関する意見(自由記述)の一覧は、資料2−4に示すとおりである。
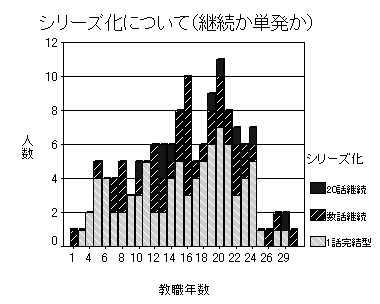
図表2−14 教職年数ごとのシリーズ化についての意向
放送番組を利用しやすい学年について尋ねた質問【質問項目2-7】では、全体の78.6%にあたる110人が「学年には関係なく利用できる」を選択した。図表2−15に、担当学年ごとの使いやすい学年についての意見をまとめた。
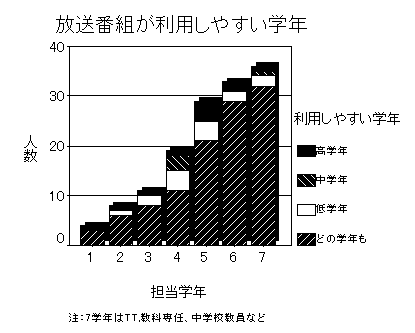
図表2−15 担当学年ごとの使いやすい学年についての意見
小学校の担当学年がある回答者のうち、自分の学年以外が使いやすいと回答した割合は、全体の7%(10人)のみであった。担当学年、性別、教職年数ごとに異なる傾向は見られなかった。回答者の72.5%にあたる103人が放送番組の使いやすい学年について記述した回答を、資料2−5に示す。
学年ごと,ないしは低・中・高学年ごとに,対象を定めて制作・放送されていることについて尋ねた項目【質問項目2-8】では、「現行のままでよい」としたのが111人(79.3%)で、「2・3年,4・5年など(低中高学年という区切りをまたいで)複数学年を対象とする番組制作すべきだ」との意見の18人(12.9%)や、「番組はすべて単独の学年を対象とすべきだ」を選択した11人(7.9%)を大きく上回った。回答者の46.5%(66人)から寄せられた対象学年についての意見については、資料2−6にまとめて示す。
今後どのような教科・領域等の学校放送番組を増やしてほしいかを尋ねた項目(複数回答可)【質問項目2-9】の回答結果を図表2−16に示す。理科と社会を上回る希望が寄せられたのは、「総合的な学習」に対応した番組であった。道徳には希望があまりなかったが、これは現在の番組以上に「増やして欲しい」との希望がないだけであって、現在の番組そのものが必要とされていないという意味ではないことに注意が必要である。
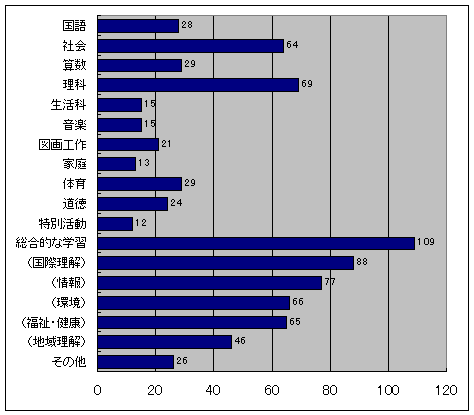
図表2−16 学校放送番組を増やしてほしい教科・領域等(複数回答)
再放送について、現在の同一番組が2週に渡って2回または4回再放送されている(最も多い場合)ことについて尋ねた項目【質問項目2-10】では、図表2-17のような回答があった。現行の方式をサポートする意見が多かった一方で、より多くの再放送を望む声と回数を減らしても問題ないとする意見が同数程度あり、ナマ利用と録画利用を前提とした立場が反映されている結果となった。
図表2-17 再放送についての意見
——————————————————————
現行と同じでよい(2回または4回)・・・90人
放送は,2回程度あればそれでいい・・・24人
それ以上の再放送を望む・・・・・・・・22人
放送は,1回だけでいい・・・・・・・・・5人
——————————————————————
放送時間帯について質問した項目【質問項目2-11】では、夕方以降あるいは午後の放送を望む声が多く、ここでは、録画を前提にした回答になっていることが示唆された(図表2-18)。
図表2-18 放送時間帯についての意見
——————————————————————
夕方以降(深夜を含む)にも放送してほしい・51人
午後の時間帯にも放送してほしい・・・・・・48人
現行のままでよい・・・・・・・・・・・・・37人
朝早い時間帯にも放送してほしい・・・・・・6人
——————————————————————
学校放送番組を利用するための重要な条件を尋ねた項目(複数回答可)【質問項目2-12】の回答結果を図表2-19に回答数の多い順に示す。時間帯が限られた放送を補って利用しやすくするためのライブラリーやVOD(ビデオ・オン・デマンド)、あるいは映像素材や補足教材などの提供を望む声が多く、次いで、利用アイデアや番組内容の工夫、案内の充実と続いた。その他の意見としては、「学級の小さなテレビで、どれだけ番組制作の方の意志が伝わるか常に不安」、「番組の中に子供達が存在すれば、もっともっと身近に感じる」などがあった。利用促進の面からは、「学校内に限り取捨選択や加工が可能な視聴形態を許す番組」の提供などの具体的なアイデアも見られた。
図表2-19 学校放送番組を利用するための重要な条件
——————————————————————————————
ビデオライブラリーやVOD等による二次利用体制の確立・・103人
番組で使用した映像素材、画像素材の教育利用のための提供・102人
番組に関連した補足教材等の提供・・・・・・・・・・・・・65人
利用アイデア(例えば実践プラン)の提供・・・・・・・・・64人
番組内容・構成のいっそうの工夫・・・・・・・・・・・・・53人
番組案内(放送内容等)の充実・・・・・・・・・・・・・・51人
放送番組利用に関する実践研究組織の拡充・・・・・・・・・35人
テレビやVCRの設置環境の充実・・・・・・・・・・・・・23人
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10人
——————————————————————————————
←第1章第2節「調査の方法」・第2章「調査結果」第1節 回答者のメディア利用実態・第2節 放送番組についての教師の期待・第3節 番組ごとの意見と期待→