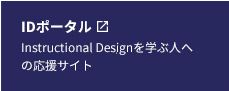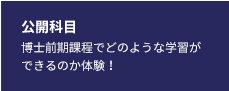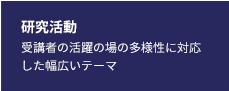第16期生 落合道夫さん

落合 道夫さん 第16期生
福岡女学院中学校・高等学校 教諭
現在のお仕事について簡単にご紹介いただけますか
私立中学校・高等学校で理科・物理の授業を担当しています。授業では、基礎概念の理解はもちろん、実験やICT機器を活用した探究的な学びを重視し、生徒が自ら問いを立て、考え、表現する授業づくりに取り組んでいます。
また、アクティブ・ラーニングの視点を取り入れ、生徒同士の対話や共同を促す授業展開にも力を入れています。
本専攻に入学しようと思ったきっかけを教えてください
本専攻の主催する公開講座(基礎編・応用編)に参加し、ID(インストラクショナルデザイン)の考え方に触れ、授業づくりに大きな示唆を得ました。その後、科目等履修生としてさらに学ぶ中で、IDをより体系的に深めたいと思うようになりました。
個別の科目だけでは不十分であり、修士課程で本格的に学ぶ必要があると感じ、本専攻への入学を決めました。
実際に入学されて、いかがでしたか
当初はIDを学びたいと考えていましたが、実際にはそれ以外にも多くの学びがあり、それらが有機的につながって「教授システム学」という体系として理解できたことが大きな収穫でした。入学前は研究テーマが明確ではありませんでしたが、自分に合ったテーマに出会うことができたことも幸いでした。
また、共に学び合い、支え合える仲間と出会えたことは、この専攻で学ぶ価値をさらに大きくしてくれました。
学んだことは、どのように役立っていますか?
学んだことは、授業力の向上に確実に結びついています。とくに、研究テーマとして取り組んだジャスト・イン・タイム教授法を実践することで、これまでにない形の物理教育を展開できるようになりました。
また、今後重要となる探究学習に対応する実践力を身につけられたこと、加えて、学術論文を書く力を指導していただけたことも非常に有益でした。
とはいえ、学んだ内容は幅広く、そのすべてをまだ十分に活用しきれていないとも感じています。今後は、それらを現場や研究に生かせる場を積極的に探し、実践につなげていきたいと考えています。
普段は、どのように学習を進めていましたか?
普段は、早朝に学習の時間を確保するよう心がけ、休日にはできる限り学習に充てる時間をまとめて取るようにしました。
科目ごとの課題を常に把握しておくと、日常のふとした瞬間に課題解決のアイデアが浮かぶことが多く、それを逃さないようメモし、翌朝の時間にレポートとして整理する、というサイクルで学習を進めていました。
学生間のコミュニケーションはどのようにとられていましたか?
同期生とのコミュニケーションは主に Slack を用いて行っていました。数人で構成するプロジェクト課題では、Zoom 会議も実施しました。また、月に1回程度、同期生全員に声をかけて Zoom で情報交換会を開き、それぞれの取り組み状況や悩みを共有することができました。
先生とのコミュニケーションはどのようにとられていましたか?
2週に1回の Zoom でのゼミが中心でした。必要に応じてメールでもやり取りをさせていただきました。研究を進める際には、2週ごとのゼミで進捗を報告し、適切な指導を受けられるよう、そのサイクルに合わせて計画的に研究を進めるよう努めました。
専攻を修了して得た収穫はなんですか?
実践と理論を往還しながら学べる力が身についたことです。当初はID(インストラクショナルデザイン)を学べればよいと考えていましたが、教授システム学の体系そのものに触れたことで、授業づくりをより広い視点から捉え直せるようになりました。
また、自分に合った研究テーマに出会うことができ、修了後も引き続き研究を続けていられることも収穫です。そして共に学び合える仲間を得られたことも大きな財産です。さらに、ID以外の領域にも視野が広がり、今後の研究や実践に生かすための確かな土台ができたと感じています。
最後に、これから入学を考えている人にメッセージをお願いします
私は50歳代になってから入学しましたが、「学ぶのに遅すぎる」ということは決してありません。むしろ社会経験を積んだ今だからこそ、学びが深くつながり、実践に生かせる場面が多いと感じています。
この専攻では、年齢や背景の異なる仲間とともに学び合える環境があります。少しでも関心があるなら、ぜひ一歩を踏み出してみてください。学ぶことは、新しい視野と仲間を与えてくれる、とても豊かな経験です。
(2025年11月メールインタビュー)
※ 登場している方々のご所属および本専攻のカリキュラムや科目に関する記述は、インタビュー当時のものです。