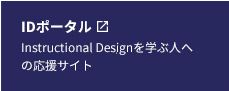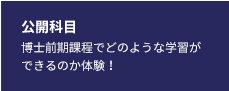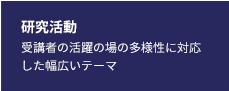博士後期
博士後期課程は教授システム学分野における研究能力を育成するため、必修科目(4科目)と選択科目(8科目)の合計12科目からなる多彩な科目で構成されます。
|
分野
|
科目名
|
選択/ 必修 |
1年
|
2年
|
3年
|
|||
|
前期
|
後期
|
前期
|
後期
|
前期
|
後期
|
|||
|
社会科学的研究方法(教育学領域)
|
量的研究法演習 |
選択 (A) |
◎
|
○
|
○
|
|||
| 質的研究法演習 |
◎
|
○
|
○
|
|||||
| 教授システム設計研究論演習 |
○
|
◎
|
○
|
|||||
| 教育政策・戦略研究論演習 |
○
|
◎
|
○
|
|||||
|
情報学的研究方法(情報学領域)
|
コンテンツ開発研究法演習 |
選択 (B) |
◎
|
○
|
○
|
|||
| 学習支援システム開発研究法演習 |
◎
|
○
|
○
|
|||||
| コンテンツ評価研究論演習 |
○
|
◎
|
○
|
|||||
| マルチメディア利用研究論演習 |
○
|
◎
|
○
|
|||||
|
共通
|
教授システム学研究総論 |
必修
|
●
|
|||||
|
研究 指導 |
総合演習 |
●
|
●
|
|||||
| 特別研究Ⅰ |
●
|
●
|
||||||
| 特別研究Ⅱ |
●
|
●
|
||||||
|
開講時期凡例 ●: 必修科目 ◎: 選択科目(この時期の履修を推奨するもの) ○: 選択科目(この時期の履修も可能なもの) *選択(A)、(B)からそれぞれ1科目以上を履修する。 |
|
社会科学分野の研究手法として、教授システム学の研究事例に即して量的にデータを扱う研究法の基礎を学ぶ。統計的手法(パラメトリック及びノンパラメトリックを含む)をいつどのように用いるのか、実験計画法(準実験法を含む)の長所と短所などを扱う。量的研究法を用いた研究事例を見たとき、統計手法及び実験計画の妥当性が判断できるようになることを目指す。
|
|||
| オムニバス方式
全15回 |
久保田 真一郎/15回 |
||
|
社会科学分野の研究手法として、教授システム学の研究事例に即して質的にデータを扱う研究法の基礎を学ぶ。観察・面接・フィールドワークなどの質的研究法の実際、グラウンデッドセオリー・エスノメソドロジーなどとその背景にある構成主義的・学習科学的アプローチ、質的分析ツールの演習などを扱う。質的研究法を用いた研究事例を見たとき、分析手法の選択及び研究手続きの妥当性が判断できるようになることを目指す。
|
|||
|
自らの研究計画案の立案に資するため、教授システム設計手法・モデル・理論の研究動向を踏まえて、様々な研究実例に関する比較検討を演習します。とくに、情報通信技術を応用した教育実践、学習者中心設計、自己管理学習を指向したインストラクショナルデザインモデルなどを中心に扱います。内外の研究事例を参照しながら、研究知見を整理する方法、教育実践から研究課題を抽出する方法、研究計画の独創性を高める方法などを学びます。ある研究テーマについて、先行研究のレビューを行い、それを独自の研究計画案作成に活かすスキルの習得を目指します。
|
|||
| オムニバス方式
全15回 |
教授システム設計手法・モデル・理論の研究動向の紹介を主に担当する。 |
||
|
|
|||
|
自らの研究計画案の立案に資するため、教育システムレベル及び教育機関レベルでeラーニングの在り方を規定する制度的・組織的諸要因の研究動向を踏まえて、様々な研究実例に関する比較検討を演習する。特に、教育実践を取り巻く政策環境、グローバル化を含む教育市場の動向、機関のポリシーや戦略、システム・機関両レベルでの質保証、マネジメント等を中心に扱う。内外の研究事例を参照しながら、研究知見を整理する方法、教育実践から研究課題を抽出する方法、研究計画の独創性を高める方法などを学ぶ。ある研究テーマについて、先行研究のレビューを行い、それを独自の研究計画案作成に活かすスキルの習得を目指す。
|
|||
| オムニバス方式
全15回 |
令和8年度は開講せず |
||
情報学的研究方法(情報学領域)
|
eラーニングコンテンツを単なる「教材」という枠にとどめず、より広く総合的にとらえることで、効果的な教育の企画・設計・実装に関する知識やスキル、研究手法を学ぶ。
eラーニングコンテンツの目標、形態・構造、リソースに応じて、最適な開発法(コンセプト、プロセス、技術、リソース調達)を検討、選択、立案できることを目指す。コンテンツ開発に関わるサンプルケースを、教育方法論的、情報通信技術的、マネジメント論的な観点から分析をおこない、その妥当性を判断・議論することを経て、サンプルケースの発展や応用を提案する。 |
|||
| オムニバス方式
全15回 |
令和8年度は開講せず |
||
|
工学分野の研究手法として、教授システム学の研究事例に即して学習支援システム開発の視点から研究法の基礎を学ぶ。学習支援システムの機能的分類と、機能毎の実装方法及びその開発環境、システム間連携と標準化などを扱う。学習支援システム開発に関する研究事例を見たとき、用いられている開発手法の妥当性が判断できるようになることを目指す。
|
|||
| オムニバス方式
全15回 |
|||
|
自らの研究計画案の立案に資するため、コンテンツ評価手法・理論等の研究動向を踏まえて、様々な研究実例に関する比較検討を演習します。とくに、情報通信技術を活用した教育活動履歴からの評価データ取得方法、アンケート等学習者からの評価データ取得方法、データ解析の理論などを中心に扱います。内外の研究事例を参照しながら、研究知見を整理する方法、教育実践から研究課題を抽出する方法、研究計画の独創性を高める方法などを学びます。ある研究テーマについて、先行研究のレビューを行い、それを独自の研究計画案作成に活かすスキルの習得を目指します。
|
|||
| オムニバス方式
全15回 |
|||
|
自らの研究計画案の立案に資するため、マルチメディアの分類と活用手法・知的財産として法的権利、義務等の研究動向を踏まえて、様々な研究実例に関する比較検討を演習する。とくに、ネットワーク通信帯域や映像・音声等のデータ圧縮手法、インターネット上の国際的な知的財産権などを中心に扱う。内外の研究事例を参照しながら、研究知見を整理する方法、教育実践から研究課題を抽出する方法、研究計画の独創性を高める方法などを学ぶ。ある研究テーマについて、先行研究のレビューを行い、それを独自の研究計画案作成に活かすスキルの習得を目指す。
|
|||
| オムニバス方式
全15回 |
戸田 真志/15回 マルチメディアの分類と活用手法の研究動向の紹介と、関連する様々な研究実例に関する比較検討の演習を主に担当する。 知的財産として法的権利、義務等の研究動向の紹介と、関連する様々な研究実例に関する比較検討の演習を主に担当する。 |
||
共通
|
本科目では、教授システム学分野における研究動向の全体像を俯瞰できるよう、各専任教員が専門性を持つテーマごとに研究動向を概観します。教授システム学関係領域における広範な研究動向をカバーし、これらの研究動向に対する幅広い関心と視野の上に立って、自ら専門的な研究を遂行できるようになる基礎の涵養を目指します。各担当教員は、授業の中で教授システム学分野全体における当該担当テーマの位置付けや意義の明確化を図ることとし、学生が自らの研究の位置付けや意義を認識しながら研究する能力を身につけられるように配慮します。
|
|||
| オムニバス方式
全15回 |
|
||
研究指導
|
学生ごとに指導担当教員を定め、最新の理論成果や実践的課題を素材としながら、研究関心に応じた適切な研究計画を作成する演習を行うとともに、他の学生や教員と一緒に集団的に研究計画案・研究経過を発表・討論し合い、個別研究指導と協調学習の組合せで研究計画を具体化し、その質を高めていく。協調学習の最終回においては、各自作成した研究計画書に基づき、進捗を総括するとともに、研究計画に沿った次のステップを確認する。この科目修了時には、目的・意義と方法論の明確な研究計画がほぼ固まる。
|
|||
|
学生ごとに複数の指導担当教員が博士論文作成に向けての研究指導を行う。研究の進捗状況を定期的に報告させ、質疑応答や助言・コメントを通じ、研究計画に沿った着実な進捗(必要に応じ計画の軌道修正)に導く。第一次報告及び第二次報告の機会を設け、他の学生や教員と一緒に集団的に研究経過を発表・討論し合い、協調学習による研究の質の向上を図る。この科目修了時には、論文の骨格がほぼ固まり、学位論文のテーマが決定される
|
|||
|
学生ごとに複数の指導担当教員が博士論文執筆の研究指導を行う。論文執筆の進捗状況を定期的に報告させ、質疑応答や助言・コメントを通じ、学位論文として必要な水準にある論文の完成に導く。論文草稿を発表する中間発表の機会を設け、他の学生や教員と一緒に集団的に報告・討論し合い、協調学習による論文の質の向上を図る。論文審査時に行われる最終発表において、十分な学術的水準を備えた学位論文の完成とともに教育研究者又は研究能力を活かす高度専門職業人としての資質の修得を確認する。
|
|||